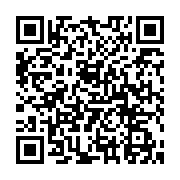アート / コラム・論文
Posted on 2025-02-20
絵画の価値(価格)はどう決まる?
M&C編集部 蓬田修一
「絵画」と書きましたが、広く美術品と捉えてお話してみたいと思います。
それと「価値」と書きましたが、美術品にはいろいろな「価値」が備わっていますが、ここでは「価格」に焦点を当てます。
なぜ価格の高い作品があるのか?
答は「高くてもいいので、その作品を欲しい」と考える人がいるからなのですが、そのことをもう少し掘り下げてみましょう。
なぜ高額になるのか? 有名コレクターがコレクションを始めた
ふたつのエピソードをお話します。
以前、都内の美術館にゴッホの展覧会を見に行きました。
それは海外のあるコレクターのゴッホコレクションを中心に構成されている展覧会だったと思います。
会場には、そのコレクターの説明パネルがありました。
それによると、ゴッホは当時、今のような有名な画家ではなく、どういう経緯かは忘れましが、このコレクターがゴッホ作品を気に入り、作品を購入し始めました。
このコレクターは美術界隈では有名コレクターで、美術関係者たちは「あの有名コレクターがコレクションを始めたのだから、ゴッホという画家の作品は将来価値が出る(価格が高くなる)」と考えて、ゴッホ作品は価格が上がったのだそうです。
美術関係者が高値で購入する
もうひとつのエピソードをご紹介します。銀座でギャラリーを運営する会社の社長(日本人)が書いた本で読んだことです。
1980年代のバブル経済のころ、日本人のある実業家(製紙会社の会長だったかと思います)が、正確な金額は忘れましたが、240億円だったでしょうか、莫大な金を出して、ヨーロッパの近代絵画の作品を2点買ったことがあります。
本を書いたギャラリーの社長はこのことに対して「私だったらこんな金の使い方はしない!」と言っています。
「もし240億円あったら、私だったらアメリカの美術館に入ってしまった、いくつもの雪舟の絵を高値で買い戻す。そうすれば世界の美術市場において雪舟の価値が高まる。日本絵画の最高峰ともいえる雪舟の価値が高まれば、ほかの画家の作品も、それにつられる形で価格があがる。そうやって、日本美術全体の価値を上げていきたい」
こういう趣旨のことを書いていました。
ほかの国、例えばアメリカも中国も、美術界と国を挙げてこういうことを行い、自国の美術の価値を上げている、と言います。
需要と供給で価格が決まるのではない
需要と供給の均衡という空想的な経済理論で価格が決まるのではなく、国家や美術関係者が作り出した経済環境で価格が決まるのが実態だと考えています。
これは以下に書きます、美術作品をめぐる投機と投資にもつながります。
投機家と投資家
将来値上がりするものを安いうちに買って、値上がりしたら売ろうという行為を「投機」と言います。
特定の作家の作品が値上がりしそうだということが分かれば、絵画に投機する人(投機家)が増えます。
同時に、投機ではないけれど、いま持っている自分の資産の一部を絵画に変えて、そこから金銭だけではない様々な将来的リターンを得ようと考える「投資家」も増えます。
こうした投機家と投資家が増え、絵画の価格はますます上がっていくことになります。
価値は自然発生的に高まらない
こうみてきますと、絵画の価値は人々の人気などが高まり、それにともなって上がっていくという素朴なものではないと考えております。
世の中のごく一部の美術関係者や国家の考えや思惑で変化していくものなのだと思います。
いまはこんな風に考えています。(2025年2月)
Related Posts