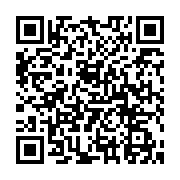アート / 特集記事
Posted on 2025-03-11
春を思わせる西洋絵画名作10選
冬の寒さを過ごした身に、日に日に増す春の訪れは、からだのなかに眠っていた何者かを目覚めさせてくれるかのようだ。
西洋絵画の歴史をひもとくと、どの作品も「春」の持つ生命力や美しさを、それぞれの時代の視点や画家の関心で描いていて興味深い。
中世から印象派まで、春を思わせる名作を10点を選んだ。
(M&C編集部・蓬田修一)
《春(プリマヴェーラ)》 サンドロ・ボッティチェリ(1482年頃)
ルネサンスを代表する作品。ギリシャ神話が題材と考えられ、春の訪れを祝う女神フローラ(画面右側にいる、花の衣装をまとった女性)が描かれている。
《ベリー公のいとも豪華なる時祷書 4月》 ランブール兄弟 (1485年~1489年頃)
中世フランス王国の王族ベリー公ジャン1世が作らせた時祷書(じとうしょ)である。
時祷書とはキリスト教徒が用いる祈祷文、賛歌、暦などを記した書物のことだ。私的なものであり、所有者が趣向をこらして作成することがあった。
本書は国際ゴシックの傑作と言われている。
《田園の奏楽》 ジョルジョーネ(1509年頃)
田園の風景の中で音楽が奏でられ、ふたりの裸婦と貴族風の服を来た男、質素な身なりの男が描かれている。
いくつもの解釈がある作品で、主題などははっきり分かっていない。
季節は春というより初夏を思わせるが、今回は春の絵画として選んだ。
印象派のマネはこの作品に着想を得て、1863年に《草上の昼食》を描いた。
《フローラ》 ティツィアーノ・ヴェチェッリオ (1515年頃)
ヴェチェッリオは盛期ルネサンスにおいて、ヴェネツィアで活躍した画家だ。
この女性は誰であるかは議論されていて、恐らく高級娼婦であろうと考えられている。
彼女の右手に握られている春の花から、春または植物の女神である「フローラ」として解釈されることが多い。
《春》 ジュゼッペ・アルチンボルド(1563年)
アルチンボルドは4枚の肖像画連作《四季》を描いた。この作品は、そのうちの1枚である。若い女性と思われる人物が描かれている。
神聖ローマ帝国皇帝、ハプスブルク家のマクシミリアン2世に贈られた。
《暗い日》 ピーテル・ブリューゲル(1565年)
ブリューゲルは初期フランドル派の巨匠である。
これは《早春》とも呼ばれる作品だ。
ブリューゲルは6点の季節画連作を描いたが、そのうちの一番始めの作品である。2月か3月頃の早春に季節は設定されている。
《モルトフォンテーヌの思い出》 カミーユ・コロー(1864年)
バルビゾン派の画家コローが描いた風景。
コローは、アカデミズム絵画(ルネサンス→新古典主義の流れを汲む絵画)を学んだあと、新しい潮流バルビゾン派をつくった。のちの印象派に大きな影響を与えた。
《草原で花を摘む少女たち》 ピエール=オーギュスト・ルノワール(1890年)
草原に背の低い樹木が生えている。ふたりの可憐な少女が花を摘み遊んでいる。
ルノワールは独特の軟らかいタッチで、少女の絵をいくつも描いた。
《果樹園》 カミーユ・ピサロ(1872年)
ピサロは1869年から1872年まで、パリ郊外のルーヴシェンヌで暮らした。
この地は保養地として文学者や画家がたびたび訪れ、別荘地でもあった。
ピサロはここに住んでいたとき、この作品を描いた。
彼はサロンに出品していたが、サロンでの評判は芳しくなかったので、出品はしないようになった。
彼は1874年の第1回印象派展にこの作品を出展した。
《春》 クロード・モネ(1873)
モデルはモネの最初の妻カミーユだ。
ライラックの花畑に座って、日陰で読書をしている。
《春》 アルフォンス・ミュシャ(1896)
ミュシャはアール・ヌーヴォーを代表する画家。アール・ヌーヴォーとは、19世紀から20世紀初頭にかけてヨーロッパで花開いた美術運動で、「新しい芸術」を意味する。
ミュシャは《四季》と題して、春、夏、秋、冬の連作を描いた。
この作品はそのひとつである。
Related Posts