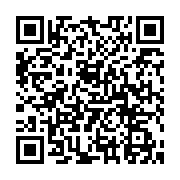アート / 特集記事
Posted on 2025-03-13
「死」をテーマにした西洋絵画 名作10選
死は人間にとって避けては通れない現実であり、それを画家たちはどのように描いたのか。
西洋絵画史において「死」を扱った10作品を選び紹介する。(M&C編集部・蓬田修一)
《アルノルフィーニ夫妻の肖像》 ヤン・ファン・エイク(1434年)
ヤン・ファン・エイクはフランドル(現在のベルギー西部を中心とする地域)の画家。
一見すると結婚の祝福を描いた肖像画だが、アルノルフィーニの亡くなった最初の妻への追悼画であるという説がある。
《死の勝利》 ピーテル・ブリューゲル(父)(1562年頃)
ピーテル・ブリューゲルはブラバント公国(現在のベルギーおよびオランダの一部)で活躍した。
ブリューゲル自身が自分について何も書き残していないこともあり、生涯については謎に包まれている。
《死の勝利》は、14世紀にヨーロッパ全土を襲ったペストの恐怖を反映した作品。
死が誰の上にも容赦なく襲い掛かり、壮絶な状況となっている。
《聖母の死》ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ (1604~1606年)
カラヴァッジョが登場したのはルネサンス期の後だ。
16世紀末から17世紀初頭にかけてローマ、ナポリ、マルタ、シチリアで活躍した。
人間の姿をあたかも映像のように写実的に描き、光と陰の明暗を明確に分ける表現で見るものに衝撃を与えた。
彼の作品は、バロック絵画の形成に大きな影響を与えた。
この作品の特徴はその大きさにある。人物はほぼ等身大で描かれている。
聖母マリアは真っ赤なドレスを身に着け、ぐったりと横たわる。
腕は垂れ下がり、膨らんだ足を伸ばしている。
その様は、聖母といえども死の運命から逃れられない、生々しい現実を描写している。
ここには聖母の神聖さはなく、宗教画に見られる聖人への敬意もない。
サンタ・マリア・デッラ・スカラ教会の礼拝堂のために制作されたが、品位に欠けるとして物議をかもし、教会には納品されず、最終的にはルーベンスの勧めで、イタリア・マントヴァ公国のヴィンチェンツォ1世・ゴンザーガ公爵が購入した。
《サムソンとデリラ》 ピーテル・パウル・ルーベンス(1609~1610年)
若い女性の膝の上に、屈強な男性が気持ちよさそうに眠っている。
その男性の髪の毛を、後ろにいる男が切り落としている。
この絵の背景をまず説明しよう。
旧約聖書「士師記」によると、イスラエルの人々が悪に走ったため、神はイスラエルをペリシテ人に与え支配した。
あるときイスラエル人の女性が神の導きによって子供を産む。
その子はサムソンといい、神から特別な力を与えられていた。
成長すると超人的な怪力の持ち主となり、ペリシテ人を打ちのめしたのち、20年にわたって士師(裁判官)としてイスラエル人を指導した。
サムソンはデリラという女性を愛した。それを知ったペリシテ人は銀1100枚の報酬でデリラを買収し、サムソンの怪力の秘密を聞き出そうとした。
サムソンの怪力の秘密は、彼が生やした長い髪にあった。
秘密を知りたがるデリラに対して、サムソンはなかなか本当のことを話そうとしない。
しかし、髪を切ると力を失うことをついに話してしまった。
そこでデリダはペリシテ人を呼び寄せ、サムソンを自分の膝の上で眠らせたあと、彼の頭から髪をそり落とさせた。
サムソンは怪力を失い、ペリシテ人に捕えられた。
彼は両眼をえぐられ、獄中で辛い労働をする日々となった。
サムソンは獄中で次第に髪を伸ばし神に祈る。
ある日、ペリシテ人は鎖につながれたサムソンを見世物として宴会を開いた。
神の力を受けたサムソンは、宴会場の柱を押した倒し宮殿を倒壊させペリシテ人を殺すが、この戦いで自分も死んでしまう。
ルーベンスのこの作品は、サムソンがデリラに裏切られ、死へと向かう運命を暗示している。
《キリストの死を悼む2人の天使》 グエルチーノ(1617~1618年頃)
グエルチーノは本名をジョヴァンニ・フランチェスコ・バルビエーリという。
グエルチーノとは「やぶにらみ」という意味で、彼が斜視だったことから付けられたあだ名である。
バロック期の画家で、ローマ、ボローニャで活躍した。
この作品では、磔刑の後、十字架から降ろされたイエス・キリストの隣で、ふたりの天使が静かに瞑想し跪いている。
《オフィーリア》 ジョン・エヴァレット・ミレー(1851~1852年)
シェイクスピアの戯曲『ハムレット』の登場人物、オフィーリアの死を描いたラファエル前派の名作だ。
オフィーリアはデンマークの貴婦人。度重なる悲しみのあまり狂い、川に溺れて死んでしまう。
この作品は流されながら、歌を口ずさんでいる姿を描いている。
《メデイア》 フレデリック・サンズ(1868年)
フレデリック・サンズはラファエル前派の画家。
ボヘミアン的なライフスタイルを好み、借金をつくって妻に捨てられた。
ロマ(ジプシーのこと。近年はロマということが多い)の女性と遊んだり、若い女優と付き合っていた。
女優とのあいだには9人の子供がいるという。
この作品のモデルはロマの女性、ケオミ・グレイだといわれる。
絵画の中のメデイアは魔女であり、怪しげな物質を燃やし、ヒキガエルをそばに置いて、誰かを呪い殺すのか、謎の呪文を唱えている。
《死の島》 アーノルド・ベックリン(1880年)
スイス出身の画家、アルノルト・ベックリン(1827年 – 1901年)の代表作。
ベックリンは1880年から1886年の間、「死の島」をテーマにした作品をくり返し描いている。
神秘的な島へと漕いでいく船の様子が、死の世界へと向かう旅を想起させる。
《戦争》 アンリ・ルソー(1894年)
ルソーは19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの画家。
伝統的な絵画の教育を受けず、独学で絵を描いた。
そのため画力が劣っていると言われることもあったが、次第に伝統教育を受けていないがゆえの独自の表現技法が高く評価されるようになった。
パリの税関に勤めていたが、50歳を過ぎたころに退職し年金生活に入り、全人生を絵画制作に振り向けた。
この作品は、少女が馬のような奇妙な動物とともに空を飛び(あるいは動物にまたがり?)、気持ち良さそうに駆け回っている。
画面下方に目を向けると、いくつもの屍が転がり、カラスがついばんでいる。
戦争の恐怖を幻想的に描いた作品だと言われている。
《マラーの死》 エドヴァルド・ムンク(1907年)
ムンクは19世紀末から20世紀前半にかけて活躍した、ノルウェーの画家だ。
この作品は、フランス革命の指導者、ジャン=ポール・マラーの死がテーマになっている。
ムンクはこのテーマで2作品を描いた。これはそのうちの1点だ。
Related Posts