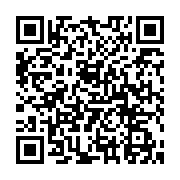アート / 歴史 / 特集記事
Posted on 2025-04-11
中国古代から近代まで名画10選
中国の絵画史は、紀元前から始まり非常に長い。
今回は、古代から近代までの代表的な絵画を時代順に10点紹介する。
古代から順に作品を見ることで、絵画の特色の変遷が分かり、中国絵画の魅力を感じることができたので、これまで中国絵画に関心が薄かった人も、自分の興味を惹いた作品からでよいので、是非、見てほしい。
《馬王堆一号墓出土品 T型帛画》(前漢 紀元前168年頃)
帛画(はくが)とは、帛と呼ばれた絹布(細かく織った絹)に描かれた絵画をいう。
紙が使われる前は、紙の代わりに絹布が使われた。
私は紙を発明したのは蔡倫という人物だと思っていた。
高校の世界史の授業で、そのように勉強した記憶がある。
実は、紙は紀元前2世紀頃、すでに中国で発明されおり、後漢時代の西暦105年頃に、蔡倫が改良して実用的な紙ができあがった。
ということで、帛画というのは、蔡倫が紙を改良する前、古代中国の春秋戦国時代から漢代にかけて描かれたものである。
春秋戦国時代も漢代(前漢)も、紀元前というとても古い時代なので、帛画は古代思想を調べる手がかりとして、考古学的に価値がとても高いものだ。
本作は、貴人(王の夫人)の棺の蓋の上に、絵のある面を死者に向けて広げられていた。
絵のテーマは、死後の霊魂が不死の世界である仙界(具体的にはヒマラヤの近くにある崑崙山)へ昇るという「昇仙」である。
上の画像では暗くて判読しにくいと思うが、全体は、天上・地上・地下の3つの世界で構成されている。
画面下段は地下の世界。
中段の地上世界では、墓に埋葬された夫人が、杖をついて横向きに立っていて、夫人の霊魂が、龍の舟に乗って、仙界へと飛び立たんとしている。
上段は天上界である。
2200年前の絵師たちは、夫人の死後の世界を想像し、不死の願いを込めて昇仙の有様を描いた。 中国古代における精神世界の魅力がつまっている。
《女史箴図》顧愷之(東晋・4世紀)
女史箴(じょししん)とは、西晋の恵帝の皇后賈后が、帝の暗愚なのに乗じて、専横放縦を極めたのを諷刺して、女子の誡めを説いたものをいう。
中国南北朝時代に編まれた「文選(もんぜん)」という書物の中に記載されている。
文選は、中国の歴史にとっては重要な書物である。
官吏登用試験「科挙」の受験者必須の書物であり、詩人も愛読した。
日本でも奈良時代は貴族の必読書で、その後、室町時代頃まで教養の書として読み継がれてきた。
顧愷之は「画聖」と称えられるほどの実力の持ち主で、博学であり、頭の回転も速かった。
変わり者かもしれないが、魅力ある人物だったように思う。
彼は、女子の戒めの内容を絵で表現した。
上に紹介した絵はその一部で、作品全体はいくつもの場面が描かれた長い巻物になっており、合計27人の男女が描かれいる。
彼ら彼女らが身に付けている衣服や、周囲の調度品などは、古代を知るうえで貴重な史料でもある。
オリジナルは大英博物館に収まっており、日本では東北大学に、小林古径、前田青邨の模本がコレクションされている。
《洛神賦図》張僧繇(南朝梁)
曹植(そうしょく/そうち)の詩「洛神賦(らくしんふ)」に基づくロマンチックな物語絵である。
曹植は、魏の皇族であると同時に、李白、杜甫以前における代表的な文学者でもある。
賦とは 文体的には漢詩と散文の中間に位置する文学作品だ。
漢代から清朝まで2000年以上、連綿と続いて来た。
本作だが、本来は物語全体が巻物の体裁で描かれている。上には、巻物の最後の場面を載せた。
洛神とは,伝説上の皇帝である伏羲(ふくぎ)の女,宓妃(ふくひ)が洛水(らくすい)で溺死したが、その後、神となったものをいう。
曹植は兄の文帝曹丕(そうひ、魏の初代皇帝)の妻,甄氏(しんし)を思慕していたが、父曹操の命によって、その想いは叶わなかった。
洛神賦は、甄氏との悲恋を,洛神宓妃との交流という形をとって書かれたものだというのが伝統的な見解である。
ちなみに、甄氏は「傾国の美女」として知られている。
《歴代帝王図巻 蜀の昭烈帝(劉備)》 閻立本(7世紀)
閻立本(えんりっぽん)は、唐時代の貴族であり画家でもあった。
唐王朝二代目皇帝太宗に仕え、宮廷画家として活躍した。
人物図および肖像画を得意とする。
「歴代帝王図巻」は前漢の昭帝から隋の煬帝までの歴代13人の皇帝を描いたものだ。
本作だが、閻立本の手によるものではなく、北宋時代の模写との見方が強い。
《瀟湘図》董源(10世紀)
董源(とうげん)は、五代十国時代の南唐およびその後の統一王朝北宋初期の画家である。
人物画と風景画で知られる。
特に風景が有名で、優雅なスタイルで描き、風景画の創始者とされている。
瀟湘とは、湖南省にあるふたつの河川、瀟水(しょうすい)と湘水(しょうすい)が合流して洞庭湖に注ぎ込む一帯の地名だ。
古くから風光明媚な場所として知られる。
《谿山行旅図》范寛(北宋初期)
北宋時代、山水画は大きく発展する。
范寛(はんかん)は、北宋初期の風景画家だ。
自然観察にもとづく水画(風景画)を追求した。
本作は、山頂を下から仰ぎ見る構図で描かれている。
高い山が眼の前にそそり立つようである。
《桃鳩図》徽宗(伝1107年)
作者の徽宗(きそう)は、北宋第八代皇帝だ。
政治的には無能であったが、画人としては才能が高く評価され、宋代画壇を代表する人物のひとりである。
「風流天子」と称されたことからも、徽宗がどのような皇帝であったが察せられる。
宋代を代表する画家ともなれば、画業に費やす時間は膨大であり、その分政治に費やす時間は少なかったであろうし、実際、徽宗は国を豊かに強くする政治を行わなかった。
徽宗は自らの奢侈のために民衆に重税を課した。
民衆の恨みは高まり、反乱が続発した。
反乱指導者の中に、山東で活動した宋江という人物がいた。
彼をモデルにした野史(朝廷によって書かれた歴史書ではなく、民間で書かれた歴史書)や講談から発展して誕生したのが、今でも人気のある文学作品「水滸伝」である。
☆ ☆
本作《桃鳩図(ももはとず/とうきゅうず)》は、およそ30センチ四方の色紙サイズの小さな作品である。
本作は、日本と深いゆかりがある。
足利義満が所持し、明治時代は井上馨の所有であった。現在は個人が所蔵していて、国宝に指定されている。
個人蔵だけに、展覧会などに出品される機会は稀で、10年に1度程度しかない。
しかも展示期間は数日から1週間ほどで、国宝界の“ハレー彗星”と呼ばれる所以だ。
展示されている機会があれば、是非とも見ておきたい一品である。
《廬山高図》沈周(1467年)
沈周(しんしゅう)は、明代中期の画家である。
文人画(ぶんじんが)の一派である呉派を興し、「南宋文人画中興の祖」とされた。
文人画とは、職業画家ではなく、文人(儒家としての教養を身に付けた支配階級)が余技として描いた絵画のことをいう。
沈周は絵画だけでなく、蘇州文壇の元老としても中国文学史上に名をとどめ、書家としても活躍した。
詩書画三絶の芸術家として後世になっても評価が高いスーパースターである。
家訓を守り生涯にわたって仕官することがなかったという変わり者だ。
83歳で亡くなったから、当時としては高齢であり、大往生である。
本作《廬山高図(ろざんこうず)》は、実景ではなく、空想の世界が描かれた作品だ。
沈周は本作を師である陳寛の古希祝いに描いた。
山の崇高なイメージを借りて、師匠の徳行を表現している。
前景に描かれた、流れ落ちる滝を見上げる人物は、李白の「望廬山瀑布」の詩意をもとにした創作であろう。
《黄山八勝画冊 第五図 鳴絃泉 虎頭岩》石濤(清初)
石濤は明王朝の末裔として生まれる。
父親は明王朝が滅びると、空位となった帝位につこうとしたため、明の亡命王朝や新王朝である清朝から狙われ、最終的には捕らわれて獄死した。
幼かった息子の石濤は、父親の臣下によって助け出され、明や清の官憲から身を隠すため出家した。
僧侶となった石濤は絵画と書を学んだ。
特に山水画に秀でて、既成の画法に捉われない独特な画風を創り出した。
明王朝遺民でありながら、清王朝の康煕(こうき)帝に2回謁見して、作品を奉上している。
愛新覚羅博爾都(あいしんかぐら ぼると)が生涯のパトロンとなり、51歳で僧籍を捨て、画業に専念。晩年は画作で生計を立てた。
《Tree And Man (selfportrait)》徐悲鴻(1932年)
徐悲鴻は、清朝末期の1895年に江蘇省無錫に生まれた。
1916年に復旦大学法文系に入学。1917年に日本に留学。1919から27年まで、国費留学生としてフランスのパリ国立高等美術学校へ留学し、西洋の絵画を学んだ。
フランス留学中は、ドイツをはじめヨーロッパ各国に赴き、絵画の勉強に励んだ。
1927年に中華民国に帰国し、上海、北京、重慶の芸術学校で教育に携わった。
中華人民共和国が成立したあとは、国旗、国章、国歌の制定に関わった。
1950年、中国で最も著名な美術大学である中央美術学院の初代院長に就任した。
Related Posts